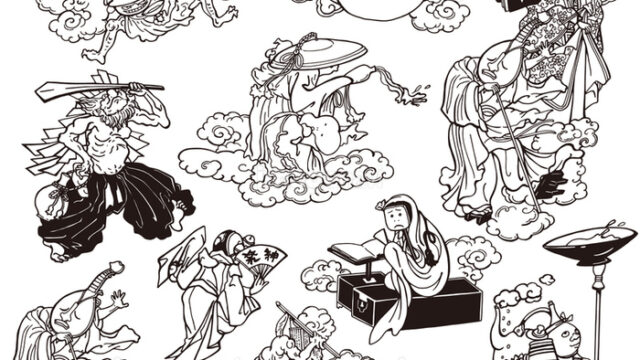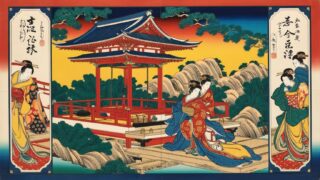徳川埋蔵金伝説とは?
日本の歴史都市伝説の中でも、最も有名なものの一つが「徳川埋蔵金」。
江戸幕府が滅びる前、徳川家が莫大な財宝をどこかに隠した――そんな噂が、150年以上も語り継がれています。テレビの特番でも度々取り上げられ、発掘プロジェクトも数多く行われました。しかし、いまだ決定的な発見はありません。
今回、ねこ君が、このミステリーの全貌と真偽に迫ります!

そもそもなぜ徳川埋蔵金は有名なのか?
伝説の始まりは、明治維新によって徳川幕府が崩壊した1868年。
「幕府が最後の切り札として、江戸城や甲府、日光、群馬の赤城山などに金銀財宝を隠した」という話が人々の間に広まりました。
時代が進むにつれ、「埋蔵金が見つかれば一攫千金!」と夢を見る人々が、全国で発掘に挑みます。
特に、昭和・平成時代にはテレビ番組で度々「本気の発掘」が行われ、一大ブームに。未だに新たな発掘話が尽きません。
根拠・証拠はあるのか?
文献・記録からの検証
実は、江戸幕府が財宝を隠したという公式な記録や史料は、現在まで一切見つかっていません。
一部では、旧幕臣や関係者が書き残した「財宝がある」とされる書簡や証言が伝わっていますが、その多くは伝聞や噂に近いものです。
発掘の歴史
明治以降、さまざまな場所で「ここに埋蔵金がある」と発掘が行われてきました。
特に群馬県の赤城山、日光、静岡の駿府城跡などは「有力候補地」として何度も掘られていますが、金貨や小判がザクザク…なんて成果は今のところゼロ。
テレビでよく出てくる「怪しい巻物」や「暗号」も、出どころが不明なことが多く、信憑性には疑問が残ります。

なぜ埋蔵金は見つからないのか?
1. 江戸幕府に「隠すほどの財宝」はなかった説
幕末の徳川幕府は、長い戦争と借金で財政難だったのが事実。
「隠せるほどの大金はなかった」「すでに使い果たしていた」という歴史家の意見も根強いです。
2. 財宝を隠した記録が一切残っていない
将軍家や幕府の記録は非常に細かく残されていますが、肝心の「埋蔵金を隠した」という公的記録はゼロ。
これは“作られた伝説”の可能性を高めます。
3. 明治新政府の財政事情
もし幕府が金銀を大量に隠していたなら、明治新政府が財政難の時に何らかの形で発見・回収されたはず――という指摘もあります。

【徳川埋蔵金】伝説スポットMAP!徳川埋蔵金伝説スポット”を紹介
1. 群馬県・赤城山
伝説の宝が眠るとされる最有力候補地。明治時代から多くの発掘が行われ、今も埋蔵金伝説の聖地。
2. 静岡県・駿府城
徳川家康の隠居城。「駿府城下に財宝が隠された」とする説あり。近年も“発掘ブーム”が起きた。
3. 栃木県・日光(東照宮近辺)
家康の霊廟がある日光。神聖な土地だけに「秘宝が隠された」との都市伝説が語られる。
4. 山梨県・甲府(武田信玄ゆかりの地)
武田家の財宝=徳川に渡った説から、「甲府近辺に隠した」話も。
5. 東京都・江戸城跡(皇居周辺)
江戸城内、今の皇居にも財宝が眠るという噂が根強い。ただし発掘は困難。
おまけ【都市伝説検証】徳川埋蔵金の暗号
江戸幕府が滅びるとき、徳川家は財宝の隠し場所を“暗号”で残した――。
そんな噂が全国でささやかれています。古文書や巻物、石碑に刻まれた謎の文字。
その真偽はともかく、現代でもたくさんの「徳川埋蔵金の暗号」が出回っています。
【例1】「赤城山の巻物に残された謎の文」
東西南北、岩の影。
二つ目の松、五歩下がって水を掬え。
その下に黄金あり。
【例2】「家康の書状に残されたと噂される謎」
三つ葉葵は東を指す。
日が沈むまでに三度、石を叩け。
【例3】「駿府城に伝わる暗号」
月の夜、影を踏みて北に歩むべし。
水の流れ止まる所、そこに宝は眠る。
【おまけ2】ざっくり適当に考察解読してみた
東西南北、岩の影。
二つ目の松、五歩下がって水を掬え。
その下に黄金あり。
これをいったん考察・解読してみましょう。
まず暗号文を分割してみた
「東西南北、岩の影。」
「二つ目の松、五歩下がって水を掬え。」
「その下に黄金あり。」
それぞれの意味を考えてみよう
1. 「東西南北、岩の影。」
場所のヒント:「東西南北」という表現から、現地に方角を示す何かがある。例えば大きな岩や石碑など。
「岩の影」:太陽の動きや、特定の時間帯にできる岩の影を指している可能性。例えば「昼に南を向くと岩の影がどこに落ちるか」など。
伝説の多い赤城山など、現地に巨石・岩場が多い場所だと特に重要なヒント。
2. 「二つ目の松、五歩下がって水を掬え。」
「二つ目の松」:現地に松の木が並んでいる。二本目の松が基準点。
「五歩下がって」:松から五歩(現地での歩幅=1歩約70cmとして約3.5m)離れろ、という具体的な指示。
「水を掬え」:水が地表近くにある(=井戸、小川、湧き水などがある)ポイントを示す可能性。または地下水脈を示唆?
3. 「その下に黄金あり。」
「水を掬える場所=地下水が湧く(井戸がある/掘ったら水が出る)」
その“下”=実際に掘ると「黄金」=埋蔵金

推理のミニまとめ
暗号は現地の自然地形(岩・松の木・水の存在)を使った「現地限定の地図」になっている。
伝説上の「赤城山」や「駿府城跡」など、巨石と松並木が揃うエリアで再現しやすい。
「二つ目の松」「五歩」など具体的な数値が入っているので、現地にしか通用しないリアルな指示。
「水を掬え」が最大のポイント。水場=古くから人が集まりやすい=財宝を埋めるなら理にかなっている。
もし最新機材をつかうなら
地図・アプリやドローンで現地の地形を調査。
最新の地中レーダーで「水脈」や「地下異物」を探知。
AI画像解析で「岩の影」や「松並木」の位置を過去の航空写真で比較。
まとめ:あなたはどう思う?
どのエリアが「本命」だと思いますか?
「水を掬える」=水脈の場所を昔の人はどう探していたのか?
他に「二つ目の松」のような手がかりが現地にないか?
など色々と考察してみるのも面白いし、休日に現地にいってついでにグルメを・・
なんて面白そうですね!
では今回はここまでとします。
有難うでした。